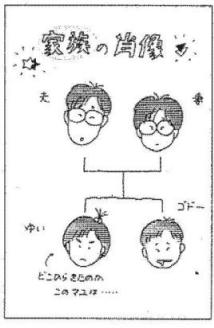1「障害児」が生まれる
何かが顔をぺたぺたさわるので目をさます。
赤ん坊の息子が起きてきて顔をさわっている。
時計を見ると6時。
なんとか寝たまま相手をしようとするのだが、根負けする。
「もう少し寝かせてくれえ」と言いながら抱き上げ、寝室から居間へ向かう。
息子は8ヵ月になる。
何にでも手をのばし、どこにでも這って行ってしまう。居間と台所の間には、既成のつっぱり棚のフェンスを取りつけているのだが、息子がつかまり立って、大声で何やらだでぃだでぃ言いながら膝の屈伸運動をしている。
急いでミルクをつくって息子に手渡すと、口が迎えにくる。
最近、息子は仰向けにしてやれば、哺乳瓶を自分の手で支えて飲めるようになった。
早朝の台所に響くジュー、ジューというあぶくの音を聴いていると何とも言えない健やかな気持ちになる。
音を噛みしめながら新聞を読んでいると、しみしみした泣き声が聞こえている。
3歳になる第1子の唯生が目をさました。
泣き声が大きくならないうちに唯生のミルクをつくる。
1回分240ccのうち30cc分は別の哺乳瓶に分けて薬を混ぜる。
泣き声がだんだん大きくなってくる。
唯生は、今朝の4時に寝かしつけたときと同じ格好で横向きに寝ている。
骨ばった肩に手をあてて抱き上げると大粒の涙がぽろぽろ頬をつたう。
ほおずりして唯生のにおいを確かめると涙も口に入ってきてしょっぱい。
「唯生、おはようおはようおはよう。さあミルクにしよう」
だっこしてミルクをやりはじめる。
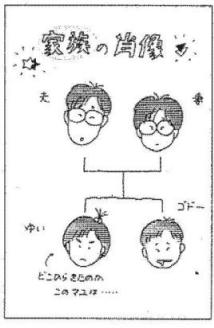
私がこのような朝を過ごすようになって7ヵ月ほどになる。
唯生は、仮死で生まれ、その後遺症で脳性マヒと診断されている。
私は今、勤め先の会社から1年間介護休暇をもらい、唯生の介護をしている。
この介護休暇とは、介護を要する家族をもつ者が1年を限度に取得することができる休暇で、私の勤め先では平成5年から導入され、私は取得第1号であった。
これまでも休日は唯生の世話をしてきたが、24時間唯生と生活してみたかったのだ。
息子の出産予定日の少し前から1年間を休暇の期間とした。
私の家族は夫婦、子ども2人の4人で、横浜市に住んでいる。
夫婦の話し合いで、この1年間は私が専ら唯生の世話をし、妻は専ら息子の世話をすることとした。
唯生は、けいれんの発作があるため、抗けいれん剤を服用している。
脳性マヒによる四肢マヒ及び精神発達遅滞があると診断されていて、1級の身体障害者手帳とA1(最重度)の療育手帳(精神薄弱児/者の手帳)の交付を受けている。
脳性マヒとしては最重度だ。
首が座っていなくて、手足を自分の意志で動かすことや物を目で追うことがほとんどできない。
唯生が生まれた日のことは、今でも雲の上にいるようなふわふわした感じで、現実感をもてない。
昼すぎにお産になるでしょうから昼食を食べてきてください、と看護婦さんに言われ、分娩室を離れていると食堂に電話が入った。
緊急に帝王切開になります、とのこと。
急いで戻ると、手術の承諾書への署名が求められ、その後は待合室で落ち着かない時間をつぶした。
5月の穏やかな日差しが差し込んでくる。
出産には必ず立ち会おうと思って、五種類の呼吸法も練習して妻より上手なぐらいになり、いつでも撮影できるようにビデオカメラも用意してきたのに、役に立たなかったなあと、気楽なことを考えていた。
看護婦さんが分娩室を慌ただしく出入りしていた記憶がある。
仮死でしたと教えられ、唯生に初めて会ったのは、手術開始後5、6時間たった後だったような気がする。
唯生は保育器に入っていて、酸素吸入を受けていた。
体中に脂肪が分厚くついていた。
元気に生まれた子ならば産湯ですっかりきれいにしてもらえるのだろうに、と思ったら、長くは会っていられなかった。
妻は1週間で退院した。
それから唯生が退院するまでの1ヵ月間、妻は毎日母乳を絞り、私は2日に1回、早朝出勤前に冷凍母乳を届けた。
病棟に行くとガラス越しに唯生に会わせてもらえた。
そのたび、様子と体重を妻に電話で伝えた。唯生は少し神経質そうだが、順調に元気になっているように見えていた。
しかし退院を控えての主治医の話は予想と全く違っていた。
重い障害が残るだろう。身の回りのことをなんとか自分でできるくらいで、知能は養護学校についていくのがやっとという程度だろう、というのが彼の見立てだった。
それがどんな「程度」を意味するのかはよくわからなかった。
面談後、妻と2人でどこをどう歩いて駐車場の車に戻ったのか覚えていない。
ドアを閉めると、どちらからともなく「どうしよう」と言ったきりしばらく黙っていた。
少しでも唯生と離れているのが嫌で、三日後の退院を明日にしてもらうように言いに行くことにした。
病棟に行けば、さっきの話は間違いでしたといわれるように思えた。
私たちは、「障害児」が生まれたとなれば医師や役所の人々が次々に現われて、どんどん色々な手続きを進めてくれて、ただ親はおろおろしていればよいのだと思っていた。
しかし、唯生が退院したとき、私たちは一ヵ月後の診察の予定以外何ももたず、私たちがそのまま川に身を投げたとしても、誰もそれを関知しないのだった。
それからの私たちは、唯生の障害を告げられた日の病棟と車との間を行ったり来たりしていたようなものだった。
「脳性マヒ」や「障害児」といった言葉にだけ過敏に反応し、なんて不幸をしょいこんでしまったのだろうと思ったり、そういった言葉を使いさえしなければ事態が改善されるように思えたり、どこかに別の診断をしてくれる医師はいないものだろうかと思ってみたりした。
2へ
戻る