私も妻も、このころを思い出すと話は尽きない。
担当のF先生と園のおかげで、私たちは安定して実りの多い日々を過ごすことができた。
F先生との出会いから、夫婦だけで抱えていた唯生の問題を初めて第三者と共有することができるようになった。
私も妻も、キラキラ星園の先生たちが手作りした修了証がとても気に入り、居間の壁に飾った。
和紙の切り紙が貼ってあり、子どもたち1人1人に違った言葉が添えられた修了証だ。
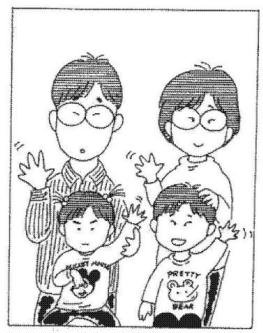
6唯生が連れてきた人々
私の1年間の介護休暇が終わる日、私と妻は吉祥寺のイタリア料理のレストランで食事をすることにした。
私たちは、ベビーシッターに子どもたちを任せて外出できるようになっていた。
唯生は3歳4ヵ月、息子は11ヵ月。
私と妻は、ワインを飲みながら食事をし、この一年のさまざまなことを話し合った。
私はそのために、一年間の出来事をメモにして持ってきていた。
最初にベビーシッターさんを派遣してくれたのは「横浜ベビーシッターサービス」という会社だった。
それまで、唯生はシッターさんに見てもらうのは嫌だろうと思えていたし、引き受けてくれるところがあるとも思っていなかった。
しかし、友人の結婚式の出欠を迷っていたとき、妻は思い立って電話帳を片手に次々に電話をかけた。
「そういうお子さんはちょっと……」という返事に、「やっぱりなあ」と思いかけるころ、「ハンディキャップを持つお子さんとそうでないお子さんと何の違いがあるでしょうか。お預かりしない同業者がいるということは恥ずかしいことです」と言ってくれたのがその会社だった。
やってきたシッターさんは、紙風船をポンポン飛ばして、唯生と息子を同じようにあやしてくれて、私と妻が遅く帰宅したときには、2人並んで深い寝息をたてていた。
確かに2人とも何の違いもないようだった。
息子は、私が唯生のための介護休暇に入ってまもなく生まれた。
よく晴れた体育の日だった。
息子を看護婦さんが連れていったあと、私は病院の会議室で仮眠をしたが、日差しがまぶしくてしかたなかった。
病棟で私と妻は、喉を鳴らすようにしておっぱいを飲んでいる息子を見ていて、新しい元気な赤ん坊に夢中になった。
そしてその分、唯生はこれまで親から背負わされていた重荷を降ろすことができたように思う。
障害を持つ唯生の親であり、健康な息子の親であることは、それぞれ幸せなことに思えた。
息子は元気に生まれたものの、そのあと妻が大変だった。
産後検診で残留胎盤を掻き出す処置をした後、出血が止まらなくなり、その日の夜に緊急入院した。
子どもたちを残していくわけにもいかず、唯生と息子も車に乗せて、家族で病院に向かった。
私が子ども2人を連れて社宅に戻ったのは夜中の1時を回っていたと思う。
車を降りると息子を先に3階の部屋まで運んで、引き返して唯生を連れに戻った。
そのとき、唯生と目が合ったような気がした。
真っ暗な車の中で唯生は力強く穏やかに微笑んでいるかのようだった。
「ごめんね。ごめんね」とつぶやきながら唯生を抱えて階段を昇った。しばらくすると、2人とも6時間ぶりに大泣きを始めた。
この1年で一番楽しかったのは、唯生が通った脳性マヒ児のための療育施設「キラキラ星園」での4ヵ月だ。
私も妻も、このころを思い出すと話は尽きない。
担当のF先生と園のおかげで、私たちは安定して実りの多い日々を過ごすことができた。
F先生との出会いから、夫婦だけで抱えていた唯生の問題を初めて第三者と共有することができるようになった。
私も妻も、キラキラ星園の先生たちが手作りした修了証がとても気に入り、居間の壁に飾った。
和紙の切り紙が貼ってあり、子どもたち1人1人に違った言葉が添えられた修了証だ。
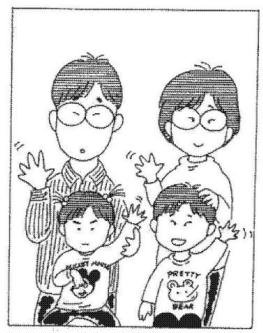
「あなたは4ヵ月の間、キラキラ星園の訓練をがんばってきました。
キラキラ星の歌が誰よりも好きで素敵な笑顔をたくさん見せてくれました。
これからもいろいろな人に愛され楽しい日々を過ごしてください」
「2月になってからが忙しかったね」と私が言う。
キラキラ星園が閉園になることが決まり、私たち家族は新しい生活を組み立てなければならなかった。
「唯生と息子を連れて、行ったり来たりしてたわね」と妻。
新たに通園する施設を、あちこち見学して回った。
これほど多くの障害児たちと先生たちに会ったことはなかった。
どの子も生き生きとして、大切にしてもらっていた。
どの町にもそれぞれのキラキラ星園があるようにも思えてきた。
4月から唯生と私は週3日、横浜市の療育センターに、2日は「つくしんぼの会」という障害児の親の自主訓練会に通うことにした。
市の施設は立派だった。
特に唯生はプールの時間が大好きで、はしゃいで水をばしゃばしゃ蹴った。
つくしんぼの会では、畑の中にある福祉作業場の広間を借りて、ボランティアの人たちを中心に遊戯の時間と食事会が持たれた。
週に1回同じ場所で「おもちゃ図書館」が開設されて、主婦らしき人が楽しげにボランティアとして働いていた。息子のためにもおもちゃを借りて帰った。
この1年で、子連れで遊ぶことにも大分慣れた。
ミスタードーナツや廻転寿司の店にもどんどん入った。
私が胸に息子を抱いて、首をのばして寿司を頬張っていると、バギーで待っている唯生に店の人が「ちょっとだからね。いい子ね」と声をかけてくれた。
図書館に入ると、書棚の向こうから唯生のゴーゴーという息遣いが聞こえてきた。
振り向いている人もいたが、音が移動して書棚の端から妻と唯生の姿が見えると、私は何だか得意な気持ちがした。
「女性フォーラム」という横浜市の施設にも入ってみた。
なぜもっと早くのぞいてみなかったのかと後悔した。
保育園のような立派な託児所があり、託児時間外には授乳室として使えた。
音楽会・セミナー・料理教室等、さまざまな催し物があるようだった。
私たちはさっそく、「唯生の会」という団体を作り、アフリカの太鼓をやっているT君を呼んで音楽会をやった。
唯生は太鼓の振動で体があたたかくなってよく眠れたようだった。
私が唯生と離れて家事をしたり妻と過ごすための時間を作るために、市役所にお願いしてホームヘルパーさんに来てもらった。
初めてやってきたYさんの印象は「地味な人だった」と妻は言う。
唯生をキラキラ星園の先生以外の人に任せるのは心配だったし、元気がない人なので勤まらないのではないかと思ったが、Yさんは「一生懸命やらせていただきます」とだけ言って、言葉どおり一生懸命、唯生に接してくれた。
唯生は知らない人からはなかなかミルクを飲みたがらなかったし、唯生の食欲は慣れない人には計り難いようだった。
最初私は別室にいて、なかなか唯生が泣きやまないと出て行ってミルクをやっていたのだけれど、Yさんは「少しずつ慣れますから」と言って道に出たり公園に連れていったり、唯生を何時間もあやしてくれて、2〜3ヵ月のうちに、ついに唯生の信頼を勝ち得たのだった。
後に、「ヘルパーで障害児に慣れている人は少ないし、私も初めてなので、自信はなかったけれど、やれるところまでやろうと思いました」と話してくれた。このような人の経験にプラスになったことは、私と同じ境遇の人のためにもよかったと思った。
横浜市の社宅が閉鎖されることになり、8月に東京都杉並区に転居した。
杉並区でも新しい通園先を2つかけもちした。
そこに小さいながらプールがあった。暑い夏を唯生と一緒にプールへ入るなどして過ごして、秋風が吹いてきた頃、私の1年間の介護休暇は終わりになった。
唯生と過ごしたくて取得した休暇だったけれど、唯生をめぐって多くの人々に会うことができた。
私と妻は唯生の生まれた病院で、生後1ヵ月だった唯生の障害の話を聞いて、これからどこへ行ってよいかもわからず右往左往した。
そんな私たちのことは誰も知らないし、わかってもらえないと思っていた。
でも1人ずつ声をかけてくれる人が視界に入ってきて、この1年で数えきれないほどになった。
「みんな、唯生が連れてきた人たちだね」と私と妻は話した。
私は日頃プレゼントをしないので妻には不興を買っているのだが、休暇の終わりを記念するその日は、妻にカードを贈った。
子どもの絵がたくさん描かれているカードに「有難う」と書いた。
何に対してなのか、うまく説明できないが、そういう気持ちだった。
妻は「あなたこそよくやったと思うよ」と言い、少し目を赤くしていた。
生きていればこんな1年、こんな1日もあるのだ。
(唯生のいる世界に暮らす おわり)